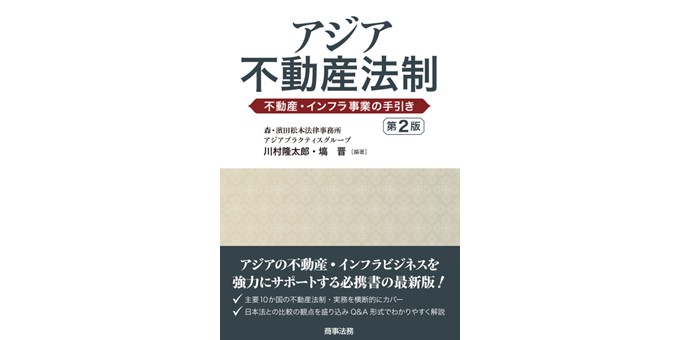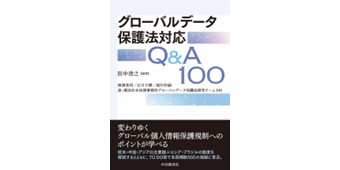Ⅰ. インドネシア:事業許認可制度に関する新政令2025年28号の施行
2025年6月5日、インドネシア政府は政令2025年28号(「本政令」)を施行し、従来のリスクベースの事業許認可制度を定めていた政令2021年5号(「旧政令」)を改正しました(これに伴い旧政令は廃止されています。)。
本政令は、従来の事業許認可取得手続等をさらに一元化・明確化するものであり、本政令下において、施行日から2025年10月5日までの4か月の移行期間中に、施行規則の制定のほか、事業許認可統合電子サービス(「OSS」)システム及び国家輸出入管理システム(Indonesia National Single Window/INSW)のアップデート等が予定されています。
本レターでは、本政令の規定する事項のうち、重要と思われるものを紹介します。
1. 事業許認可制度に関するアップデート
本政令上、旧政令下のリスクベースの事業許認可制度の枠組み(事業者が行う事業活動について、事業活動ごとに低・中低・中高・高の4段階のリスクに分類したうえで、各リスクレベルに応じて取得すべき許認可が異なる枠組み)それ自体は維持されています。
もっとも、同制度の対象業種が旧政令下の16分野から22分野へと拡大され、電子取引分野等が新たに追加されています。
また、本政令上、事業活動について、①事業開始段階及び②事業運営段階の2段階に分けられ、リスクレベルに応じて各段階において取得が必要な許認可が明確化されています。具体的には、リスクレベルが低・中低の事業活動については基礎的なライセンスのみを取得すれば事業運営を開始することが可能であり、他方で、リスクレベルが中高・高の場合には、別途、各事業分類コード(「KBLI」)ごとに定められる許認可の取得が事業運営を開始するために必要とされる建付けになっています。この点について、旧政令からの実質的な変更は大きくはないようにも思われますが、今後制定される施行規則を注視する必要があります。
2. 外資企業に対して課せられる最低資本金要件及び最低投資額要件に関する変更
本政令上は規定されていないものの、本政令の施行規則である投資省(「BKPM」)規則の草案において、外資企業の最低資本金額が、現状の100億インドネシアルピア(約9,000万円)から25億インドネシアルピア(約2,200万円)にまで大幅に引き下げられることが規定されています。現時点では、BKPM規則は施行されていませんが、最低資本金要件が大幅に緩和される可能性があります。
一方、最低投資額(原則として5桁のKBLIごと、かつプロジェクトロケーションごとに満たす必要のある最低投資額)要件は維持されています。なお、主たる事業活動ではない「支援事業活動」について、最低投資額要件の遵守義務が免除される点は旧政令から変更されていませんが、本政令により、支援事業活動によって収益を上げることも認められる旨、新たに明記されています。もっとも、金額制限は規定されておらず、施行規則で明確化されるか否かは注視が必要です。
3. みなし承認(Fiktif Positif)制度の導入
本政令において、各種許認可の申請手続の一部が法定の期間内に処理されない場合、自動的に承認されたものとみなし、次の手続に進むことを認める「みなし承認(Fiktif Positif)」の原則が明確化されました。ただし、みなし承認が付与され、最終的に許認可が取得された場合でも、事後的に監督当局が許認可の内容について評価すること自体は想定されています。
また、2025年6月24日に、BKPMにより、みなし承認(Fiktif Positif)の対象となる258のKBLIが公表されており、これには製造業や観光業等が含まれています。
本政令は、大部にわたる法令となりますが、上記記載の点のほか、引き続き明確化が必要な事項がいくつかあるように思われます。例えば、従来は中小零細企業(インドネシア株主100%の会社)のみに割り当てられていた一定の事業(例えばKBLI47111のうち、ミニマーケット形式での飲食物や煙草の小売事業)に関しても外資規制が緩和されたかのようにも読める条項等も存在するため、今後の施行規則によって明確化されることが望まれます。また、OSSシステム等のアップデートの際には、過去の傾向からも予定どおりに新システムへの移行が進まないこともあるため、システム移行の経緯も含めて引き続き注視が必要となります。
Ⅱ. フィリピン:勤務開始前の従業員解雇に関する最高裁判例
2025年4月2日、フィリピン最高裁は、外資系企業における勤務開始前の採用撤回事案(Alltech Biotechnology Corporation 対 Aragones事件(G.R. No. 251736))に関し、勤務開始前であっても、契約のオファー受諾時点で雇用契約は成立しており、会社による雇用撤回は解雇に当たり、法定の解雇事由が必要である旨を判示しました。高裁は、労働者が就任することが予定されている職務が勤務開始時点で存在しない場合には、雇用関係は成立しないと判断したのに対し、本判決では、契約のオファーに明示された勤務開始日は、雇用契約の効力発生のために成就が必要となる停止条件ではなく、契約の履行開始時期を後ろ倒しする「停止期間(suspensive period)」にすぎず、勤務開始前であっても、当事者間には既に雇用契約関係が成立しており、使用者が一方的に契約を解除する場合には、労働法上の解雇規制が適用される旨判示されました。過去の判例においては、Overseas Filipino Workerの雇用契約において、勤務開始前の雇用契約関係を否定したケースもありますが、本判決においては、海外での就労に当局の手続が必要となるOverseas Filipino Workerとは事案が異なる旨判示されております。
また、本判決では、公に認められた事由の一つである「人員過剰(redundancy)」を理由とする解雇の場合に、当該事由を立証するために会社側が提出すべき証拠を明示しています。過去の判例では、人員過剰であることを記載した宣誓供述書(affidavit)の提出のみで足りると判断されている事案もありましたが、今回の判決では、「人員過剰」を理由とする解雇を正当化するには、その証拠として、新たなスタッフ配置図、実現可能性調査(feasibility study)や提案書、職務記述書(job description)、経営層承認済みの再編計画書等の具体的かつ客観的証拠を提示することが必要であり、「世界的なリストラ方針による人員削減」といった抽象的な説明だけでは不十分であることが明確に示されました。
上記判断を踏まえ、使用者としては、雇用契約のオファー(job offer)を行う際には、勤務開始に一定の条件を想定している場合には、当該条件を明確に規定することが重要となります。
また、人員過剰を理由とする解雇に際しては、より厳格にその立証のために必要な証拠を事前に準備する必要があります。特に日系企業においては、本社主導で海外事業の方針が定められ、当該方針に基づいて海外拠点のリストラが進められることが多くみられるところです。そのような場合であっても、本社のリストラによる人員削減というだけでは解雇事由の立証として十分ではないことには留意が必要です。会社側で有効な解雇事由があることを立証できない場合、違法な解雇として責任追及がなされるリスクに直結しますので、雇用契約の締結や解雇に際しては専門家とも相談の上で十全な対応を進める必要があります。
Ⅲ. ミャンマー①:ミャンマーに対する経済制裁等のアップデート~米国による制裁の一部解除の発表
2021年2月1日のミャンマーにおける国家緊急事態宣言発出後の対ミャンマー経済制裁の概要については、本レター第121号(2021年2月号)以降の各号でお伝えしております。直近の動向は、本レター第175号(2025年5月号)のとおりですが、本稿では、それ以降の続報をお伝えします。
米国財務省外国資産管理室(「OFAC」)は、米国時間2025年7月24日付けで、2021年の政変以降、ミャンマーの軍事政権との関係を理由に制裁対象に指定されていた複数の企業及び個人を、制裁対象指定から解除することを公表しました。今回制裁対象から外れることになったのは、①KT Services & Logistics (K T S L) Company Limited及び同社グループのCEOであるJonathan Myo Kyaw Thuang、②Myanmar Chemical & Machinery Company Limited及び同社を保有するAung Hlaing Oo、③Suntac International Trading Company Limited及びSuntac Technologies Company Limited並びに同社グループを支配するSit Taing Aung等の法人及び個人であり、いずれも、2022年から2024年にかけてミャンマー国軍への軍需物資の提供等を理由にOFACによる制裁指定を受けていたものです。
2021年の政変以降、OFACは、ミャンマー国軍関係者による民主主義の否定や人権侵害行為を理由に、2025年5月まで、制裁対象を徐々に拡大する方向でミャンマーの軍事政権への圧力を強めてきました。今回、上記のような制裁の一部解除が行われた理由についてOFACは公式な見解を公表していません。一部報道では、米国の戦略的関心、特にレアアース資源をめぐる地政学的な動機が背景にあるとの見方も示されていますが、この点についても米国政府は何ら明確な説明を行っていません。そのため、過去の制裁指定時に根拠とした事実関係の見直しによるものであるのか、米国政府による対ミャンマー制裁の緩和という政策転換の一環として行われたものなのか、その他の理由によるものかといった点は明らかではありません。ミャンマーの軍事政権は、2025年7月以降、トランプ大統領の強力なリーダーシップを称賛する旨を表明し、米国政府との関係再構築に向けたロビイストの起用を行うなど、米国との関係に新たな動きが見られます。
2025年末以降に実施が予定されている総選挙を経て、米・ミャンマー関係がどのような展開を見せるのかが注目されます。
(ご参考)
Asian Legal Insights 第121号(2021年2月号)
Asian Legal Insights 第175号(2025年5月号)
Ⅲ. ミャンマー②:国家緊急事態宣言の解除
2021年2月1日の国家緊急事態宣言(「本宣言」)の発出以降の経緯については、本レター第120号(2021年2月号外)以降の関係各号でお伝えしたとおりです。本宣言は、2008年憲法に明記された「発出から原則2年間」という期間を超えて、本レター第172号(2025年2月号)でお伝えしたとおり、2025年7月31日まで通算7回の延長がなされてきました。今般、国防治安評議会(National Defence and Security Council:「NDSC」)は、2025年7月31日付けのOrder第1/2025号において、当初本宣言を発出した際の2021年2月1日付けのOrder第1/2021号を廃止し、本宣言を解除することを公表しました。なお、NDSCは、本宣言の解除に合わせて、Order第4/2025号において、本宣言下で国家運営を行ってきた国家行政評議会(State Administration Council:「SAC」)に代わる新たな政府として、国家安全保障平和委員会(State Security and Peace Commission:「SSPC」)を設立したことを公表しました。SSPCは2008年憲法に基づきNDSCが新たに組織した機関ですが、実質的にはSACの権限をそのまま引き継ぎ、今後予定されている総選挙の実施に向けて、ミャンマー国軍主導の国家体制を維持するものと見られます。
ミャンマーの軍事政権は、従前より、2025年12月以降に総選挙を実施することを明言してきました。2008年憲法の規定上、国家緊急事態宣言の終了後6か月以内に総選挙を実施すべき旨が明記されていますので、本宣言は、上記タイミングでの総選挙実施に向けて解除されたものといえます。
今後実施が予定されている総選挙については、軍事政権下で登録が認められた一部の政党のみが参加可能となる見通しであり、ミャンマー国軍による支配を正当化するために行われる演出にすぎず民主的なプロセスとは言えないとの批判もなされています。また、国家緊急事態宣言の解除後も、紛争地域とされるカチン州やラカイン州等の63郡区については、NDSCによる2025年7月31日付けのOrdinance第1/2025号により、武装勢力による活動等を理由に新たな緊急事態宣言が発令されており、これらの地域では当面総選挙の実施が見送られる見込みとなっています。こういった背景もあり、今後総選挙に向けてミャンマーの国内情勢がさらに不安定化することも懸念されます。ミャンマー政府側では、総選挙の実施確保に向けて、選挙妨害行為処罰法(Law on the Protection of Multiparty Democratic General Elections from Obstruction, Disruption and Destruction)を制定し、選挙妨害行為について死刑を含む厳罰を科すことを発表しています。また、VPN規制や電磁的方法による言論の規制について定めるサイバーセキュリティ法(概要については本レター第171号(2025年1月号)参照)も2025年7月30日付けで施行されるなど、言論統制を強化する動きも見られます。総選挙の実施に向けてミャンマーの国内情勢がどのように推移していくのか、引き続き注視していく必要がありそうです。
(ご参考)
Asian Legal Insights 第120号(2021年2月号外)
Asian Legal Insights 第171号(2025年1月号)
Ⅲ. ミャンマー③:倒産法の運用開始に向けたアップデート~倒産実務家の登録証発行申請手続の開始
ミャンマーにおける会社清算手続について定める倒産法の動向については、直近では本レター第167号(2024年9月号)においてお伝えしているとおりです。会社清算手続等の開始に際し、会社による選任が法律上必須とされている倒産実務家(Insolvency Practitioner)については、2025年8月現在も依然として所定の登録が行われておらず、法律的に有効な会社清算手続等が開始できない状態が続いています。
そのような中、ミャンマー投資企業管理局(Directorate of Investment and Company Administration:「DICA」)は、2025年7月21日より、倒産実務家の登録申請の受付を開始しました。将来的にはミャンマー会社登録システム(Myanmar Companies Online:「MyCO」)での申請手続を開始する予定とのことですが、受付開始当初は、DICAで所定の申請用紙を入手し、他の関係書類とともにハードコピーを提出する対応が必要となっています。
なお、上記の情報はDICAからミャンマー倒産実務家協会(Myanmar Association of Insolvency Practitioners Inc.:「MAIP」)宛に口頭で伝えられたものであり、公式な文書等による公表は特に行われていませんが、2025年7月中に申請書の受理自体は既に開始されているようです。申請書の実際の審査自体が既に行われているのか、今後どの時期に倒産実務家の登録が完了するのかといった具体的なスケジュールは不明ですが、倒産法の運用開始に向けた大きな進捗として今後の動向が注目されます。
Ⅳ. マレーシア:国際倒産法案の下院通過
2025年7月29日、国際倒産法案(Cross-border Insolvency Bill:「本法案」)がマレーシア議会下院(Dewan Rakyat)を通過しました。この法案は、クロスボーダーでの倒産手続に関して、マレーシアの制度を、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)の国際倒産モデル法の制度に整合させることを意図したものです。本法案の定めは多岐にわたりますが、外国での倒産手続の承認のプロセスが導入されていることが大きな点となりますので、下記のとおりご紹介いたします。
1. 適用対象
本法案は、2016年会社法3条又は1990年ラブアン会社法2条に定義される「法人」である債務者を対象とする倒産手続のみを適用対象としており、個人等は適用対象外とされています。
2. 外国手続の承認
債務者に対し、外国における倒産手続が存在している場合、当該手続において債務者の財産又は事務の更生・清算を管轄する又は当該手続の代表者として行為する権限を有する者(「外国代表者」)は、当該手続を「外国手続」として承認するよう高等法院(High Court)に申請することができます。
高等法院は、外国手続を、①外国主手続(債務者の主たる利益の中心(center of main interest:「COMI」)が当該外国に所在する場合)、②外国従手続(債務者が当該外国に事業拠点(establishment)を有している場合)に分類し承認します。(ただし、マレーシアにおける公序に反する場合には、こうした承認を受けることはできません。)
本法案において、COMIの判断基準等は定義されていませんが、登録された事業所を有している場合にはその国にCOMIがあるという反証可能な推定規定が設けられています。
外国主手続として承認されると、自動的に、(1)債務者の財産、権利、義務又は負債に関する個別の訴訟又は手続の開始又は継続が停止される、(2)債務者の財産に対する執行が停止される、(3)債務者の財産を譲渡し、担保設定し、又はその他の方法により処分する権利が停止される、という効果が生じます。これに対し、外国従手続として承認された場合には(1)(2)(3)が自動的に生じる効果はないものの、外国代表者は、マレーシアの裁判所に対し(1)(2)(3)を含めた必要な命令を発出するよう求めることができます。
Ⅴ. タイ:労働者保護法改正案-出産休暇の拡充及び配偶者育児休暇等の導入-
2025年7月16日、労働者保護法に関する改正草案(「本改正草案」)が、タイ議会下院で承認されました。本改正草案は、従業員の休暇制度として育児休暇を導入するとともに、従来の出産休暇の拡充を図るものです。本改正草案は、現在、上院で審議されており、早ければ今年中に法律として制定される見込みです。以下本改正草案の内容について、概説いたします。
1. 出産休暇の拡充
現行の労働者保護法では、女性従業員は、1回の妊娠につき、98日まで出産休暇を取得でき、このうち45日までは有給としなければならないものとされています。本改正草案は、出産休暇の取得は120日まで、このうちの有給日数を60日までと変更する内容となっており、現行法上認められている出産休暇を拡充する内容となっています。
2. 新生児看護休暇(Post-Partum Childcare Leave)の導入
本改正草案により、新生児の健康状態に応じた新生児看護休暇が新たに導入されることが予定されています。具体的には、新生児が、合併症のリスクがあると診断されたり、異常な状態にあったり、障がいがあるような場合には、医師の診断書を提出することを条件として、当該新生児の母親である女性従業員は、出産休暇に追加で15日まで休暇を取得することができるものとされています。この休暇中、使用者は、当該従業員の通常の賃金の50%以上の賃金を支払う義務があります。
3. 配偶者育児休暇(Spousal Leave)の導入
現行の労働者保護法上は、女性従業員のための出産休暇以外に出産に関連した休暇は定められておらず、出産した女性の配偶者が取得できる休暇制度は法定されていないところ、本改正草案により、配偶者育児休暇が導入されることが予定されています。具体的には、従業員は性別に関わらず、配偶者の産後90日までの間に、15日以下の育児休暇が取得できるものとされています。この配偶者育児休暇は全て有給休暇とされており、使用者は、従業員の通常の賃金の全額を支払う義務があります。
本改正草案が上院で可決され、施行された場合には、就業規則の改訂だけでなく、実務上も本改正草案の内容に沿う対応が求められることになりますので、本改正草案の今後の動向について引き続き注視していく必要があります。
今月のコラム ―インド・ベンガルール探訪記―
インドの都市といえば、首都のデリーと最大の商業都市ムンバイが有名ですが、インドで第3位の人口を誇り、IT企業の進出が盛んで、日本企業の皆様にも「インドのシリコンバレー」として有名なベンガルールを今年の3月に訪れてきましたので、探訪記をお送りします。
インドは、交通渋滞の激しいことがつとに有名ですが、実は、インドで一番渋滞が酷いのはデリーでもムンバイでもなくこのベンガルールです。インドの方も「渋滞はベンガルールが最悪だ」と口を揃えて言うほど(これは今回ベンガルールを訪れて初めて知りました。)。実際、我々もベンガルールを発つ日、最終訪問地から空港へ向かう道中、通常なら1時間程度で着くはずのところ、2時間半近くを要し、飛行機の出発に危うく間に合わないところでした(幸いなことに(インド国内便ではよくある)飛行機の遅延により事なきを得ました。)。なお、ベンガルールを訪れる前は、「ベンガルールはいわゆるインドっぽくないよ」とかねがね聞いていましたが、訪れてみたら「やはりインド」でした(個人的には「やはりインド」の方がほっとします。)。
そして、「インドのシリコンバレー」であるベンガルールを訪れた以上外せないのがテック・パーク。国内外様々なIT関連企業が集結する拠点です。我々は、Vaishnavi Tech Parkというテック・パークを訪れました。中はさながら大学のキャンパスのような雰囲気で、カジュアルな装いで自由に仕事をする空気が満ちています。我々が訪れた時間帯はちょうどランチの時間帯だったことから、食堂は学食のようで、和気藹々としたランチタイムが繰り広げられていました。一緒に溶け込んでランチをする時間がなかったのが無念でした。
さらに、ベンガルールで驚いたことは、牛肉を大手を振って食べられること。ムンバイのあるマハラシュトラ州では法律により牛肉の処理・保持が禁止されており、ついぞ牛肉にはお目に掛かれないのですが(ヒンドゥー教では牛は神聖な動物とされているため)、ベンガルールでは普通にステーキ屋があり、メニューに「フィレ」や「サーロイン」と明記されていて、心置きなくビーフを食べることができます。一口にインドと言っても、場所が変わればしきたりも変わる。インドの多様性を実感した次第です。

インド第3の都市として、ベンガルールはこれから益々注目を集めるかと思います。モールは、デリーやムンバイのモールのような「ラグジュアリー感全面」ではまだなく、地方都市の「慎ましやかモール」といった様相ですが、今後5年、10年と経るとまた変わっていくのでしょう。
ベンガルールは高地にあるため、最も暑い季節で平均32℃、最も寒い季節で平均15℃と、夏は45℃超え・冬は5℃未満のデリーと比べても気候の穏やかさには特筆すべきものがあります。
今後の発展も見据えて一度ベンガルールにも足を運んでみられてはいかがでしょうか。
(臼井 慶宜)