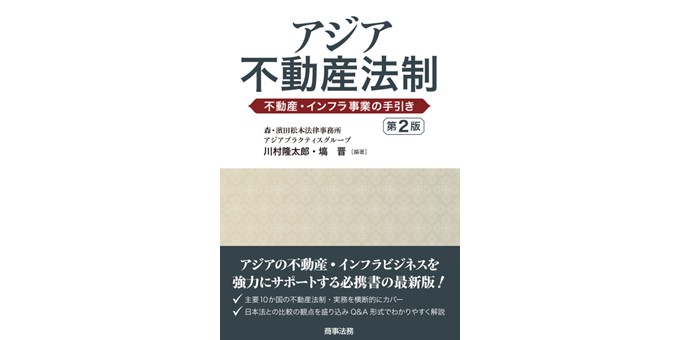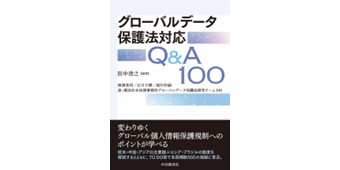Ⅰ. インド: ファストトラック組織再編手続の適用場面の拡大
インドでは、合併(amalgamation)や会社分割(demerger)といった組織再編を行う場合、原則として、国家会社法審判所(National Company Law Tribunal)の認可を取得することが必要とされ、例外的に一定の要件を満たす場合には、当該認可を取得せずに簡便な手続による組織再編(「ファストトラック組織再編手続」)を行うことが認められています。
インド企業省(Ministry of Corporate Affairs)は、2025年4月4日から同年5月5日まで、ファストトラック組織再編手続の利用場面拡大を目的とする、組織再編に関する会社法規則(Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016)の改正案(「本改正案」)について、パブリックコメントを実施しました。本レターでは、本改正案によって拡大される可能性のある、ファストトラック組織再編手続の適用範囲について、その概要をご紹介いたします。
(1) 現在の適用範囲について
現在のファストトラック組織再編手続の適用範囲は、以下のとおりです。
(a) 2社以上の小規模企業(払込資本金額が4,000万インドルピー(約6,900万円)を超えず、かつ、直近の会計年度の売上高が4億インドルピー(約6億9千万円)を超えない企業)間の組織再編
(b) 持株会社とその完全子会社間における組織再編
(c) 2社以上のスタートアップ企業間の組織再編
(d) 1社以上のスタートアップ企業と1社以上の小規模企業間の組織再編
(2) 本改正案について
上記(1)の場合に加えて、本改正案においては、以下の場合にもファストトラック組織再編手続が利用可能とされています。
(a) 2社以上の非上場会社(ただし、非営利法人であるSection 8 companiesは除く。)間の合併で、銀行、金融機関、その他の法人からの借入金が5億インドルピー(約8億6千万円)未満であり、当該返済に不履行がない場合(なお、これらの条件が満たされていることを証する監査役の証明書が必要)
(b) 持株会社とその非上場の子会社1社以上の合併の場合
(c) 同一の持株会社の非上場子会社同士の合併の場合
(d) インド国外の持株会社とインド国内の完全子会社間の合併の場合
以上のとおり、本改正案では、小規模会社やスタートアップ企業にとどまらず、一定の要件を満たす非上場会社等にもファストトラック組織再編手続を利用可能としており、インドにおける組織再編手続の簡素化が期待されます。なお、ファストトラック組織再編手続が利用可能な場合であっても、(上記のとおり国家会社法審判所の認可は不要になるものの、)株主総会において議決権の10分の9以上を保有する株主の承認を得ること及び債権者集会において債権額の10分の9以上を構成する債権者の承認を得るといった手続が必要となる点は本改正案によっても変更されません。そのため、これらの手続が引き続き必要となる点には留意が必要です。
(ご参考)
本レター第153号(2023年7月号)
Ⅱ. ベトナム: 再生可能エネルギー直接電力購入契約(DPPA)の新政令57号の施行
(1) はじめに
ベトナム政府は、2025年2月1日の新電力法の施行を踏まえ、再生可能エネルギー直接電力購入契約(Direct Power Purchase Agreement:「DPPA」)に関する新たな法的枠組みとして、2025年3月3日付けで政令57/2025/ND-CP(「政令57号」)を公布・即時施行しました。
本レター第165号(2024年7月号)でも、ベトナムにおけるDPPAに関する政令80/2024/ND-CP(「政令80号」)の施行についてご紹介しましたが、この政令80号は本格的な運用に移される前の段階で政令57号に取って代わられることとなりました。
今回、新電力法の下で制定された政令57号は、政令80号で導入されたDPPAの基本的な2つのモデル(国家送電網を利用するモデル(オングリッドモデル)と利用しないモデル(オフグリッドモデル))を踏襲しつつも、その適用範囲、参加者の適格要件、価格設定ルール、余剰電力の取扱い、契約手続等に関して数多くの重要な変更・明確化を行っています。
本レターでは、政令57号で規定されるDPPAの2つのモデルの概要を改めて整理するとともに、政令80号から政令57号への主要な変更点を中心にご紹介いたします。
(2) DPPAの各モデルの概要と政令75号の政令80号からの変更点
政令57号は、政令80号と同様、以下の2つのモデルを規定しています。
・モデル1:国家送電網経由DPPA(オングリッドモデル)
・モデル2:国家送電網を経由しないDPPA(オフグリッドモデル)
以下、各モデルの概要と、政令80号からの主な変更点を解説します。
(a) 国家送電網経由DPPA(オングリッドモデル)
●概要
- 発電事業者は、発電した電力の全量を国家送電網を通じてベトナム電力卸売市場(「VNEM」)に売電し、スポット市場価格を受け取ります。
- 大口電力需要家(又は権限を付与された小売事業者)は、電力公社・その関連会社(Power Corporation及びPower Companies:「PC等」)から必要な電力を購入します。
- 発電事業者と大口電力需要家(又は権限を付与された小売事業者)は、別途、差額決済契約(Forward Power Purchase Agreement)を締結します。この契約に基づき、両者間で合意した契約価格(基準価格)とスポット市場価格との差額を決済することで、実質的に需要家が固定価格で再エネ電力を購入するのと経済的に同様の効果を目指します。
● 政令80号からの主な変更点
- 再エネ電源の対象範囲の拡大:政令80号ではオングリッドモデルの利用は風力・太陽光による発電所を保有する事業者のみでしたが、政令57号ではバイオマス発電(設備容量10MW以上)も対象に追加されました。
- 電力購入者の対象範囲の拡大:政令80号でも規定されていた生産目的の大口電力需要家や工業団地等で電力小売を行う小売事業者に加え、EV充電サービス事業者も、オングリッドモデルの電力購入者に追加されました。
- 需要家の電力消費量基準:下記「(3)消費量基準の変更」をご参照ください。
(b) 国家送電網を経由しないDPPA(オフグリッドモデル)
● 概要
- 発電事業者は、自ら投資・開発・運営する専用の送電線・変電設備等(プライベートグリッド)を通じて、隣接又は近隣の大口電力需要家に直接電力を供給します。
- 電力価格や契約条件(期間、責任、サービス基準等)は、原則として発電事業者と大口電力需要家間の相対交渉によって決定されます。
● 政令80号からの主な変更点
- 再エネ電源の対象範囲の拡大:政令80号でもオフグリッドモデルを利用できる発電事業者は太陽光、風力、小規模水力、バイオマス、地熱、潮力、その他の再生可能エネルギーの発電事業者が対象でしたが、政令57号では電力法の定義を参照し、とりわけ固形廃棄物発電が対象に含まれることが明確になりました。
- 価格設定:政令80号では価格交渉は自由とされていましたが、政令57号では、交渉価格は当該再エネ電源種別に適用される発電価格の上限を超えてはならないという価格キャップが導入されました。
余剰電力の取扱い:政令80号でも余剰電力についてベトナム電力公社(「EVN」)等へ売電することが可能であることは定められていましたが、政令57号では、余剰電力の売電に関するルールの詳細が追加されました。
・屋根置太陽光(RTS)の場合:発電量の最大20%までをEVN又はPC等に売電可能。価格は所管機関が公表する前年の平均市場価格(ただし、地上設置型太陽光の上限価格を超えない。)。
・工業団地内のRTSの場合:工業団地内の電力小売事業者への売電も可能(価格は交渉。ただし、地上設置型太陽光の上限価格を超えない。)。
・RTS以外の再エネ電源の場合:EVN又はPC等と交渉の上、売電可能。価格・量は当該売却電源の発電枠内で決定。需要家の消費量基準:下記「(3)消費量基準の変更」をご参照ください。
【表:DPPAモデル別主な変更点の比較(政令80号→政令57号)】
| 項目 | 国家送電網経由(オングリッドモデル) | 国家送電網を経由しない(オフグリッドモデル) |
| 再エネ電源の対象 | 風力・太陽光→バイオマス追加 | 固形廃棄物発電が含まれる点が明確化 |
| 電力購入者の要件 | 生産目的大口電力需要家・小売事業者→EV充電事業者追加 | 大口電力需要家(変更なし) |
| 需要家消費量基準 | 固定値(20万kWh/月)→変動基準(卸市場規則の最低消費量基準) | 固定値(20万kWh/月)→変動基準(卸市場規則の最低消費量基準) |
| 価格設定 | 基本構造(スポット価格+差額決済)は維持 | 交渉価格→交渉価格+価格キャップ導入 |
| 余剰電力売電 | 適用なし | ルール詳細の追加(価格基準、小売売電可等) |
(3) 消費量基準の変更:両モデル共通の変更点
両モデル共通の政令80号から政令57号への変更点の一つが、DPPAに参加できる大口電力需要家の適格消費量基準の変更です。
政令80号においては初回参加時及び継続参加時ともに、「直近12か月の平均電力消費量が月間200,000kWh以上」(又は新規需要家の場合、登録時に同等の消費量見込み)という固定的な基準でした。一方、政令57号では初回参加時及び継続参加時(12か月未満の場合)の基準は、「商工省(MOIT)が公布する競争卸電力市場の運用に関する規則に定められる大口電力需要家の最低消費量基準(Minimum Consumption Threshold)」を満たすこと、に変更されました。この基準値は、将来MOIT規則が改正されれば変動する可能性があります。
さらに、政令57号では、DPPAへの参加期間が12か月以上となる場合、継続のためには「前年11月1日から当年10月31日までの期間において、(MOIT規則の)最低消費量基準を満たす電力を(EVN傘下である)PC等から購入していること」という条件が追加されました。この「PC等からの購入」要件は、条文の文言上、オングリッドモデル・オフグリッドモデル間で区別をせずに設けられているように読めます。
(4) おわりに
ベトナムのDPPA制度は、政令80号制定前から注目されてきましたが、政令80号施行後もなかなか本格的な運用にまでは至らず、そのまま政令57号の制定・施行によりルールが再度大きく変更されることになりました。政令80号におけるルールの大枠自体は維持されたものの、細かい点に踏み込めば変更点は多岐にわたり、特に適用対象の拡大、消費量基準の変更、価格キャップの導入、余剰電力ルールの詳細化等は、注目すべき要素です。
ベトナムの再エネ事業への投資に関してはルールの変更が近時頻繁になされており、なかなかその内容を正確に理解するのは難しい状況になっていますが、旺盛な電力需要を背景として投資期待の高い分野であるため、粘り強く分析・検討を継続することが求められているものと考えられます。
(ご参考)
本レター第165号(2024年7月号)
Ⅲ. ミャンマー: ミャンマーに対する経済制裁等のアップデート~米国による追加制裁の発表
2021年2月1日のミャンマーにおける国家緊急事態宣言発出後の対ミャンマー経済制裁の概要については、本レター第121号(2021年2月号)以降の各号でお伝えしております。直近の動向は、本レター第160号(2024年2月号)のとおりですが、本稿では、それ以降の続報をお伝えします。
米国財務省外国資産管理室(「OFAC」)は、米国時間2025年5月5日付けで、ミャンマーの軍閥であるカレン民族軍(Karen National Army:「KNA」)と、KNAの指導者であるSaw Chit Thu氏とその息子Swa Htoo Eh Moo氏及びSaw Chit Chit氏を、米国による資産凍結措置等の対象者(Specially Designated Nationals and Blocked Persons:「SDN」)として指定することを決定した旨を公表しました。
OFACの発表によれば、今回のSDN指定は、米国民に対するサイバー詐欺、人身売買及び密輸取引への関与を理由とするものとされています。2021年2月以降、OFACによるミャンマー関連の新たなSDN指定は、ミャンマー国軍による人権侵害行為を理由として、ミャンマーの平和、安全及び安定の脅威となる者を制裁対象とする大統領令14014号に基づき、国軍関係者を対象に徐々にその範囲を拡大する形で進められてきました。今回の制裁指定は、大統領令14014号に加え、組織的犯罪とその支援者を制裁対象とする大統領令13581号も根拠とされています。その意味では、ミャンマー国軍関係者による民主主義の否定や人権侵害行為に対する制裁を意図して行われてきたこれまでのSDN指定とは、その趣旨が若干異なるもののようにも見えます。
なお、KNAの指導者であるSaw Chit Thuはミャンマーの軍事政権への関与も理由として、英国(2023年)及びEU(2024年)により、制裁対象として指定されています。今回の制裁指定による現地事業者への直接の影響はほとんど想定し難いように思われますが、ミャンマーの政情が引き続き混迷していることを象徴する動きとして注目されます。
Ⅳ. シンガポール: マネー・ロンダリング防止関連法規の改正法の施行
2024年11月14日、シンガポールでAnti-Money Laundering and Other Matters Act 2024(「改正法」)が施行されました。本改正は、①法執行機関(LEA)によるマネー・ロンダリング(ML)犯罪の追及・起訴能力の強化、②差し押さえられた犯罪行為に関連する財産の取扱いの明確化・改善、及び③カジノ事業者に対するML及びテロ資金供与対策(AML/CFT)の枠組みを金融活動作業部会(Financial Action Task Force)の基準に準拠させることを目的とするものです。以下では、これらの目的ごとに改正法の主要なポイントについて紹介します。
(1) 改正法の概要
(a) 法執行機関(LEA)によるマネー・ロンダリング(ML)犯罪の追及・起訴能力の強化
改正法施行前までは、ML犯罪を起訴するためには、検察は、シンガポールでマネー・ロンダリングされたとされる資金について、所定の犯罪行為(「犯罪行為等」)と直接的に関連する収益であることを立証する必要があり、特に当該犯罪行為等が国外で実行された場合には、その犯罪行為等からML犯罪者までの資金の流れを立証する必要がありましたが、これが起訴に際しての大きな障壁となっていました。
改正法により、汚職、薬物取引その他重大犯罪の利得没収法(Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act)が改正され、検察は、「ML犯が、犯罪行為等による収益(criminal proceeds)を扱っていることを知っていた、又はそのように信じるに足る合理的な理由があった」ことを、合理的な疑いを超えて立証すれば足りることとなりました。これにより、海外で行われた犯罪行為等に関するMLであっても、起訴が容易になるとされています。
このほか、海外の重大な環境犯罪が犯罪行為等と指定されたり、ML、テロ資金供与、拡散金融の検知を強化するため、シンガポール各省庁間での情報共有を可能としたりするなどの改正がなされています。
(b) 差し押さえられた犯罪行為に関連する財産の取扱いの明確化・改善
シンガポール法に基づく犯罪の疑いがあるものの、国外逃亡等により音信不通となっている被疑者については、その財産が差し押さえられることがありますが、改正法によりCriminal Procedure Code(刑事訴訟法)が改正され、当該差し押さえられた財産等に関する取扱いが厳格化されることになりました。
例えば、裁判所は、逃亡した被疑者に関する捜査が継続中である場合には、差し押さえた財産を返還等してはならないなどの規定が盛り込まれ、今回の改正の結果として、逃亡中の被疑者がシンガポールへの帰国・捜査に協力しない場合には、MLその他の犯罪行為による財産的利益が没収された状態となることとなり、実効的な捜査に資するものとされています。
(c) カジノ事業者に対するAML/CFTの枠組みを金融活動作業部会の基準に準拠させること
改正法によりCasino Control Act(カジノ管理法)が改正され、カジノ運営者に対するML及びテロ資金供与対策(AML/CFT)の枠組みを金融活動作業部会基準に準拠したものとされました。これにより、カジノ事業者は、Customer Due Diligence(CDD)に際して、ML/テロ資金供与リスクに加え、拡散金融リスクをも考慮することが必要となり、また、CDDが要求される閾値については、5,000シンガポールドル(約55万円)以上のデポジット又は10,000シンガポールドル(約110万円)以上の現金取引から、4,000シンガポールドル(約45万円)以上のデポジット又は現金取引に引き下げられました。
(2) 本改正法案提出に至る背景・経緯
シンガポールでは、近年ML対策に力を入れており、2023年8月に摘発されたシンガポール史上最大規模のML事件が明るみになって以降、信頼性の高い金融市場としてシンガポールの地位を維持するため、規制強化の動きが加速しています。
今回の改正法はその最たる例ではありますが、昨年7月に改正されたシンガポール会社法において、名義取締役及び名義株主並びに実質的支配者に関する情報の登録等が義務付けられたことも、ML対策の一環となります。
※当事務所は、シンガポールにおいて外国法律事務を行う資格を有しています。シンガポール法に関するアドバイスをご依頼いただく場合、必要に応じて、資格を有するシンガポール法事務所と協働して対応させていただきます。
Ⅴ. タイ: テクノロジー犯罪とデジタル資産に関する緊急勅令の改正法案の施行
タイ内閣は、2025年4月、サイバー関連犯罪に対する法的枠組みの強化を目的とした2つの緊急勅令の改正、「テクノロジー犯罪の防止・抑制措置に関する緊急勅令(the Emergency Decree on Measures for the Prevention and Suppression of Technology Crimes B.E. 2566 (2023))の改正(「改正2023年緊急勅令」)」及び「デジタル資産運営に関する緊急勅令(Emergency Decree on Digital Asset Business Operation B.E. 2561 (2018))の改正(「改正デジタル資産勅令」)」を承認しました。改正2023年緊急勅令は、現行法制の不備を解消して、巧妙化するサイバー犯罪の脅威に対処することを、改正デジタル資産勅令は、海外からタイの消費者にサービスを提供するデジタル資産ビジネスを規制することを、それぞれ目的としています。以下では、それぞれの勅令の重要な改正点について、紹介いたします。
(1) 改正2023年緊急勅令の主要な改正点
タイ内閣は、サイバー犯罪に関連する法令を横断的に改正する目的で、2023年に緊急勅令を発令しましたが、今回の改正2023年緊急勅令は、当該勅令を更に改正する勅令となります。改正2023年勅令において改正された主要な点は以下のとおりです。
(a) 定義の修正による規制対象の拡大
2023年緊急勅令において定義された「事業者」の中に、デジタル資産事業に関する勅令(the Digital Asset Business Decree)に基づくデジタル資産事業者も含まれることが規定されました。また、「デジタル・ウォレット」及び「電子マネー口座」の定義も追加され、改正2023年緊急勅令の規制の対象となることが明確になりました。
(b) 政府機関及びサイバー犯罪に利用される可能性のある事業を提供する事業者の権限の強化
- サイバー犯罪を行う者の通信経路を遮断する目的で、国家放送電気通信委員会(National Broadcasting and Telecommunications Commission:NBTC)及び携帯電話サービスを供給する事業者に、サイバー犯罪活動に使用されている疑いのある携帯電話番号について、一時的に停止する権限が付与されました。
- 金融機関及び通信事業者は、違法な送金を防止し、不正行為に関与している疑いのある口座を凍結することが任務とされています。今回の改正により、これらの事業者には、取引を監視して、不法行為に関与している疑いのある口座を凍結する積極的な措置を講じる必要がある点が明確になりました。
(c) 広くサイバー犯罪に関連する事業を提供する事業者においてデジタル資産のウォレット番号の開示及び交換を可能にする規定の追加
(d) 通信事業者における詐欺防止のためのSMSの監視義務の導入
通信事業者には、ユーザーのSMSを監視し、明らかに詐欺と思われるメッセージを発見した場合には、当該通信事業者において自動的にメッセージを削除する義務が課されました。これは、ユーザーが当該メッセージに記載されたリンクをクリックすることで、サイバー犯罪被害に合うことを防ぐことを目的とするものです。
(e) 被害者への迅速な返金
- マネー・ロンダリングの被害者への返金を、加害者の最終判決が下される前に行うための具体的な手続が定められました。
- 被害者への返金手続及び基準は、今後省令で定められることとなります。なお、10年以内に、被害者から返還請求がされなかった場合若しくは余剰資金が残った場合には、当該資金は、マネー・ロンダリング防止基金に移管されることとなりますが、この場合であっても、元の所有者の所有者の返還請求権自体には影響はないものとされています。
(f) 罰則の強化
- 個人や組織がデータの悪用や不正利用に関与することを抑止することを目的として、個人データの売買に5年以下の禁固及び500万バーツ(約2,210万円)以下の罰金が科されるものとされました。
- サイバー犯罪の背後にある金銭的インセンティブをなくすことによりサイバー犯罪の蔓延を防ぐことを目的として、オンラインギャンブル及びデジタル資産を使用した犯罪収益のマネー・ロンダリングを行った者に対して、1年以下の禁固及び100,000バーツ(約45万円)以下の罰金が科されることが規定されました。
- サイバー犯罪に使用される可能性があることを知りながら、不完全又は不正確な情報に基づいてSIMカードを販売又は登録した個人に対する罰則が規定されました。
(g) 犯罪に使用された電気通信サービスの停止及び違法なコンピュータデータの削除
- タイ王国警察、特別捜査局(Department of Special Investigation: DSI)、反マネー・ロンダリング局(Anti-Money Laundering Office: AMLO)、サイバー犯罪オペレーションセンター等の機関は、サイバー犯罪に使用されたサービスの停止を通信事業者に命じるよう国家放送通信委員会(NBTC)に通知し、要請することができるものとされました。
- 上記国家機関等の担当官は、デジタル資産ビジネスが、適切なライセンスの付与を受けずに運営されている場合、システムから違法なコンピュータデータの削除又はブロックを命じることができることが規定されました。
(h) 広くサイバー犯罪に関連する事業を提供する事業者に対する積極的な犯罪防止義務の拡大
改正2023年緊急勅令では、(g)に述べたように、国家機関に対して、サイバー犯罪を防止するための権限を強化したことに加え、民間事業者についても、金融機関や、モバイルネットワーク、通信サービス、ソーシャルプラットフォームといった事業やその他広くサイバー犯罪に関連する事業を営む場合には、サイバー犯罪の発生を防ぐために、規制基準を遵守していることの証明を提出しなければならないものとされました。これは、民間事業者に対し、サイバー犯罪を防止するための積極的な対策及びデジタル取引を積極的に保護する役割について責任を負わせることを確保するためのものです。
(2) 改正デジタル資産勅令の主要な改正点
改正デジタル資産勅令には、タイ国外でデジタル資産に関する事業を営む事業者に対して、タイ国内の利用者にサービスを提供する場合には、タイの法令に基づく適切なライセンスの取得を義務付ける規定が含まれています。タイ国内の利用者にサービスを提供する場合とは、サービスの全部又は一部がタイ語で表示されている場合、支払いがタイバーツである場合、タイの銀行又は電子口座での支払いを受け付けている場合、取引がタイの法準拠又はタイの裁判所を管轄としている場合を指します。
今月のコラム -50年目の30/4、私が見た統一会堂-
4月中旬以降、ホーチミンの中心部は沸きに沸いていました。ド派手な立て看板、あちこちにはためく金星紅旗、脈絡なく鳴り響く花火。2025年4月30日の午前中には、サイゴン解放から50年の節目を記念して、大規模なパレードが予定されていました。そして、その2週間ほど前からリハーサルのために夕方以降は大通り等で車やバイクの通行が禁止されることもたびたびありました。
パレードは、統一会堂とその正面を走る大通り、レズアン通りを中心に行われます。統一会堂は、かつてのベトナム共和国(南ベトナム)の大統領府であり、1975年4月30日には北ベトナム軍の戦車が鉄柵を破って突入したことでサイゴン解放(陥落)を世界に印象付けた、ベトナム戦争終結の象徴的な場所です。統一会堂からほど近く、同通りに面した弊所のオフィス(下記写真参照)も突発的な交通規制の影響を大きく受けました。
4月30日夜、私はオフィスを出て、帰路につこうとしていました。パレード本番を控えレズアン通りには交通規制が敷かれていました。私は軍人と警備員とバリケードだらけの目抜き通りを渡らなければ家に帰れません。これまでの交通規制では、本番まで時間の余裕があるからか、それほど厳格な交通規制は敷かれておりませんでした。私も、厳しい顔をした軍人に対して、柔らかく話しかけて、バリケードを除けて通らせてもらっていました。しかしこの日は、パレードが数時間後に迫っていたということもあり、軍人の数、バリケードの堅牢さはこれまでより格段に厳しいものになっていました。(赤で囲んだ建物が統一会堂、手前に伸びるのがレズアン通りです。)

いつものようにいかないことを察した私は、財布の中の身分証明書と、現地で身に着け始めたベトナム語を駆使して、何とか道を渡ることに決めました。Tôi muốn đi về nhà.(I want to go home.) 歓楽街で客引きに対応するための定型文が、パレード直前の緊張状態にある軍人にも通じるのか。予期したとおり、彼らは簡単には通してくれません。遠回りをしろと軍人は言いますが、私の家も規制区域内のため、どこかでこの壁を乗り越えなければなりません。ここは現実世界。RPGのように、攻略本も裏ルートもありません。しかし、ふと、ベトナムの当局対応に関する先輩方の言葉が思い出されました。
「ベトナムの当局は担当者によって判断がまちまちなことがある。(粘り強く、あきらめるな)」
人を笑顔にする武器が無ければ、居住証明書を差し出せばいい。ベトナム語の語彙がなければ、定型文に帰宅への熱い思いを込めればいい。私は、拙いベトナム語と英語で、時に日本語で、粘り強く交渉を続けました。果たして、数時間の努力を経て、バリケードは開かれ、私は、英語を多少理解する一人の軍人に引き連れられ、空っぽのレズアン通りを渡ることができました。
左手には50年前の今日、北ベトナム軍の戦車が障壁を超えて突入した統一会堂が明かに映りました。武器はなくとも、帰宅への強い意志があれば障壁は超えられる。私は達成感と満足感を胸に眠りにつき、翌朝のパレードを寝過ごしました。(写真は、ベトナムの道端で良く売られている、心安らぐカーネーションです。)

(緒方 彰大)