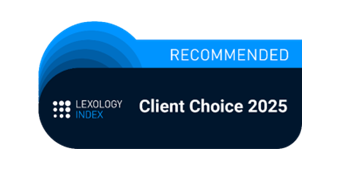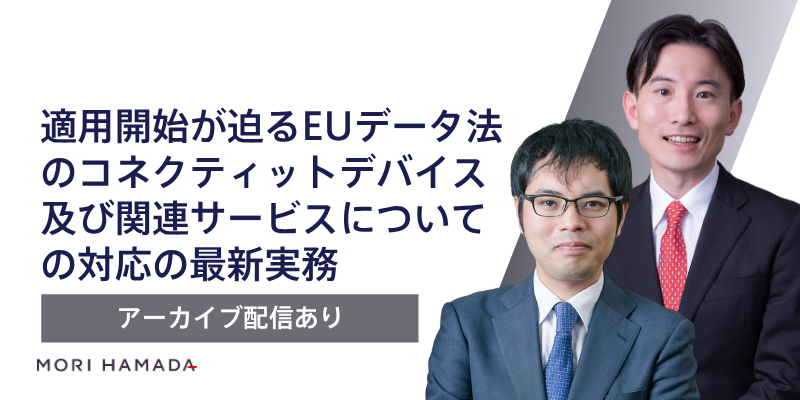(野々口 華子)
目次
-
文化芸術に関する最近の動向(~2025年3月11日)
-
1. 音楽教室における「教師」の演奏に関する著作物使用料
-「音楽教育を守る会」とJASRACが新たな規定に関する合意を発表- 【音楽】【著作権】〔野々口 華子〕
2. ニュース配信サイト運営者の配信記事に係る責任についての最高裁判断 【インターネット】〔荘司 晴彦〕 -
“文化芸術の中にある法を訪ねて(13)” 下関と「ふく」 〔奥田 隆文〕
Mori Hamada Culture & Arts Journalでは、今月も、文化芸術活動に関連する様々なニュース、裁判例、コラム等を皆さまのもとにお届けします。文化芸術活動に関心や接点を有する皆さまの気付きやアイデアの端緒・きっかけとなれば幸いに存じます。
Ⅰ. Monthly Topics
| Date | Culture & Arts Topics |
|---|---|
| 12.11 | ある記事が名誉毀損に当たる場合、その記事を転載したヤフーニュースに責任は認められるかが論点となった最高裁判断。最高裁は、ヤフーニュースは「特定電気通信役務提供者」であり、「発信者」ではないとして、ヤフーニュースの責任を否定した。 → Lawyer’s Pick 2. 「ニュース配信サイト運営者の配信記事に係る責任についての最高裁判断」 |
| 12.19 | チケットのキャンセルや転売を禁止する大阪USJのチケット規約条項につき、大阪高裁は一審に続き適法と判断1。高額転売を防止し、消費者が定価でチケットを購入できる効果があるとして、「消費者に一方的な不利益をもたらすものではない」と述べ、消費者契約法には違反しないと結論付けた。 |
| 1.21 | インスタが13歳から17歳を対象とした「ティーンアカウント」を日本でも開始。自動的に移行。 |
| 1.29 | 公正取引委員会が、映画・アニメ業界の取引の調査に向けた情報提供フォームを設置2。今回の募集で想定している情報は、契約書や発注書面がないケース、発注者から一方的に著しく低い対価を押し付けられたケース、理由もないのに発注を取り消されたケース、報酬なく無理なやり直しを依頼されたケース、無理なスケジュールを押し付けられたケースなど。 独禁法・下請法・フリーランス法上の問題について調査し、年内に報告書を公表する見通し。 |
| 1.30 | 「囲碁将棋チャンネル」(放送事業者)が有料で放送した将棋対局の棋譜分析情報について、YouTuberがYouTubeやツイキャスで配信していたことに対し、「囲碁将棋チャンネル」がYouTube動画について著作権侵害として削除申請。かかる削除申請行為について、YouTuberが損害賠償訴訟を提起。大阪高裁は、損害賠償支払を認めていた原審を取り消し、YouTuberが逆転敗訴3。YouTuberによる配信は「自由競争の範囲を逸脱し、同社の営業上の利益を侵害しているとして、不法行為にあたる」と結論付けた。 |
| 1.30 | 知財高裁は、AIは「発明をした者」(特許法29条1項)ではないなどの理由により、AIによる発明の特許性を否定した4。 |
| 2.4 | 文化庁は、地域の文化財を観光振興に活用する「日本遺産」のうち2015年度に認定した遺産の取組みを審査し、点数評価プロセスの結果を公表した5。 |
| 2.25 | JETROが「EU人権・環境デューディリジェンス法制化の最新概要に係る調査報告書」を公開した。 |
| 2.27 | 知財高裁は、GIANNI VALENTINO商標とVALENTINO GARAVANI商標につき、いずれも結合商標であるものの、「VALENTINO」を分離観察可能であるとして、商標法4条1項11号違反によりGIANNI VALENTINO商標の登録を取り消した異議決定を維持した6。 |
| 2.28 | 音楽教育を守る会と日本音楽著作権協会(JASRAC)が、新たな音楽教室規定に関して合意に至ったことを発表した。音楽教室事業者がJASRACに対して著作物使用料を支払うものとされ、大人のレッスンについては、受講者1人当たり年額750円(税別)、中学生以下(こども)のレッスンについては、受講者1人当たり年額100円(税別)とされた。 → Lawyer’s Pick 1. 「音楽教室における『教師』の演奏に関する著作物使用料 -『音楽教育を守る会』とJASRACが新たな規定に関する合意を発表-」 |
| 2.28 | 日本におけるAI新法となり得る「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案」が公開された。 |
| 3.5 | JR東日本の完全子会社「アトレ」が、テナントとの契約について、JREポイントの運営費用の一部を負担させる内容に一方的に変更していたことが判明した。公正取引委員会は「アトレ」に対し、独占禁止法違反にあたるおそれがあるとして警告した7。 |
| 3.7 | 一連の同性婚訴訟において、名古屋高裁も違憲判断を示した。 |
Ⅱ. Lawyer’s Pick
1. 音楽教室における「教師」の演奏に関する著作物使用料
-「音楽教育を守る会」とJASRACが新たな規定に関する合意を発表-
「音楽教育を守る会」8と一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は、2025年2月28日、音楽教室における「教師」の演奏に関する著作物使用料の取扱いを定める新たな規定に関して合意に至ったことを公表するプレスリリースを発表し9、同日、JASRACは文化庁に対して「使用料規程」10(以下「規程」といいます。)の変更届出を行い、規程のうち、演奏等に関する著作物使用料について定める第2章第1節に、「11 音楽教室における教師による楽器演奏等」の項目を新設することを公表しました11。プレスリリースによれば、かかる合意は、音楽文化の発展とそれを支える音楽教育の継続性、著作権の適切な保護の両立を目指し、音楽教室における著作物利用のあり方を明確にすることを目的としています。
音楽教室のレッスンにおいて演奏される楽曲の著作物使用料をめぐっては、JASRACと「音楽教育を守る会」が裁判で争い、2022年10月24日、最高裁判所の判決により、生徒の演奏は使用料徴収の対象にならない一方、教師の演奏は対象となるという判断が確定しました(本ニュースレター2022年11月号(Vol.14)ご参照。)。判決の流れは以下のとおりです。
【音楽教室の著作権使用料をめぐる判決】
| 第一審(東京地裁) | 第二審(知財高裁) | 最高裁 | ||
|---|---|---|---|---|
| 音楽教室 | 教師 | 徴収できる | 徴収できる | 審理の対象にせず (徴収できる) |
| 生徒 | 徴収の対象外 | 徴収の対象外 | ||
かかる判決を受け、「音楽教育を守る会」とJASRACは、2022年12月より、音楽教室における演奏利用のうち、教師の演奏および録音物の再生に係る使用料等についての協議を開始していました。そしてこの度、音楽教室のレッスンにおいて教師が演奏する楽曲の著作物使用料について合意に至ったとして、冒頭で触れたとおり共同名義でプレスリリースが公表され、規程に音楽教室に関する新たな項目が新設されました。
変更後の規程によれば、音楽教室事業者がJASRACに対して支払う使用料は、以下のとおりとされました。
【変更後の規程「11 音楽教室における教師による楽器演奏等」の概要】
| 大人のレッスン | 受講者1人当たり年額750円(税別) |
| 中学生以下(こども)のレッスン | 受講者1人当たり年額100円(税別) |
| 極小利用(普段は管理楽曲を使用しないが、年に数回程度利用する場合) | 1レッスンにつき1人60円(税別)~ |
| 1曲につき1人30円(税別)~ |
音楽教室事業者はJASRACと年間の包括的利用許諾契約を締結することができ、包括的利用許諾契約を締結した音楽教室事業者は、大人の生徒1人につき年間750円(税別)、中学生以下の生徒1人につき年間100円(税別)を支払い、また、包括的利用許諾契約を締結しない場合にはレッスン単位などで支払うこととなります。なお、個人で経営する教室については、使用料の支払義務が免除されています。上記変更後の規程の運用は今年4月から始まります。音楽教室事業者は、JASRACが最初に音楽教室に対して著作物使用料を請求した2018年4月まで遡って、JASRACに対して使用料を支払うことになります。
JASRACは、作詞家や作曲家などの著作権者から委託を受け、CDなどの「録音」やコンサートなどの「演奏」12、「放送」、「ネット配信」など、幅広い分野で楽曲の使用料を受け取り、権利者に分配する管理業務を行っています。JASRACは、近年、社交ダンス教室、飲食店でのカラオケ、フィットネスクラブやカルチャーセンター、カラオケ教室などにおける音楽利用も使用料の徴収の対象とし、そして、2017年には音楽教室にも請求する方針を示すなど、段階的に使用料の徴収の範囲を拡大してきました。かかるJASRACの方針に対しては、音楽文化を発展させるためには音楽家の収入源となる著作権を守るべきである一方、生徒に音楽を教える場まで徴収の範囲を広げると、逆に音楽文化の衰退を招きかねないという考え方もあったところでした。
今回の合意及び規程の変更により、音楽教室における著作物の使用に関する料金体系が明確化されたといえ、大変意義深いものであるといえます。
2. ニュース配信サイト運営者の配信記事に係る責任についての最高裁判断
報道によれば、俳優の山本裕典氏が、株式会社東京スポーツ新聞社(以下「東スポ」といいます。)及びLINEヤフー株式会社(以下「ヤフー」といいます。)を被告として、不法行為に基づき、慰謝料等の支払を求めて提起した裁判について、2024年12月11日、最高裁は、原告側の上告を退け、東スポによる原告の名誉毀損に関して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)133条1項本文の適用を認め、ヤフーに不法行為責任を認めることができないとした第二審判決が確定しました。
本件は、2020年、俳優やタレント等として活動する原告が、自ら主演俳優として出演した舞台の関係者や観覧者が新型コロナウイルス感染症に罹患するクラスターが発生したことに関し、その原因は原告らの危機意識の欠如から講演を中止にしなかった点にあるとの指摘等を主な内容とする記事(以下「本件記事」といいます。)を東スポが同社のウェブサイトに掲載したことは原告の名誉を毀損するものであり、また、ヤフーがヤフーニュースにおいて本件記事を配信したことも原告に対する名誉毀損に当たるとして、東スポとヤフーに対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案になります。
第一審は、本件記事が名誉を毀損する違法な表現であることを認定し、東スポの不法行為責任を認める一方、ヤフーについては、プロバイダ責任制限法3条1項本文が適用され、不法行為責任を認めることはできないとして、ヤフーに対する請求を棄却しました。原告は、ヤフーに対する請求が棄却された部分を不服として、控訴をしましたが、第二審も第一審の判断を支持し、ヤフーはプロバイダ責任制限法3条1項但書に定める「発信者」に該当せず、かつ、同項各号に該当する事由も存在しないとして、同項本文の適用を認め、ヤフーの不法行為責任を認めないと判断しました。
プロバイダ責任制限法3条1項は、以下のように、プロバイダを始めとする特定電気通信役務提供者の責任を一定程度限定しています。本件においては、ヤフーというインターネット上のサービス提供者へのプロバイダ責任制限法3条1項の適否、具体的には、ヤフーが同項但書の「発信者」に該当するか否か(「発信者」に該当する場合、同項の適用はなく、責任は限定されません。)が主として争われました14。
| (損害賠償責任の制限) 第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。 一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。 二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。 |
原告は、ヤフーが記事を作成する会社と記事配信契約を締結し、自ら管理するサーバを通じて、自らのウェブサイトであるヤフーニュースにおいて配信していること、ヤフーニュースから広告収入等を得ていること、社内編集部を設けて独自の掲載基準のもとに配信する記事を選定していること等に照らせば、ヤフーは、記事を作成する会社との共同事業として主体的かつ積極的に記事配信を行っていると評価すべきであり、本件記事を流通過程に置く意思を有していたということができるから、「発信者」に該当すると主張していました。これに対し、被告は、ヤフーニュースでは、新聞社や通信社が制作した記事を自ら管理サーバに入稿すると、自動的に当該記事が配信される仕組みとなっており、ヤフーは、当該記事の情報をサーバに記録又は入力をすることはないから、「発言者」に該当しないと主張していました。
本項の趣旨は、特定電気通信役務提供者が、他人の権利を侵害する情報の送信を防止するための措置を講じなかったことに関し、損害賠償責任(不作為責任)が生じない場合を明確にすることで、特定電気通信役務提供者に適切な対応を促すとともに、特定電気通信役務提供者が権利侵害をおそれるあまり、過度に発信者の表現の自由を制限することを抑止することにあり15、表現を発信する者の表現の自由と被害者の権利の板挟みの状態に陥るプロバイダに対し、一定の行為基準を与える条項とされています。
第一審及び第二審は、上記の本項の趣旨に照らして、本件記事をヤフーのサーバに記録したのは東スポであって、ヤフーが、入稿前に本件記事の内容を確認することも、入稿に関与することもなかったこと、本件記事は、ヤフーニュースのトップページに掲載されたものではなく、お勧め記事やアクセスランキング上位の記事として掲載されたものでもないことを認定し、ヤフーの「発信者」該当性を否定しました。
第二審判決では、上記のとおり、「発信者」該当性を否定する根拠として、記事の選定についてニュース配信サイト運営者の関与が認められないことを挙げているため、記事の配信や選定についてニュース配信サイト運営者の一定の関与が認められる場合には、本件とは異なる判断が下される可能性があります。
近年、ヤフーニュースを始めとして、自社では記事を執筆せず、他社が執筆した記事を配信するウェブサイトは、社会において大きな影響力を有するようになっています。本件判決は、このようなニュース配信サイトの責任について、一定の枠組みを提供したといえ、本件以降、配信サイトによって配信された記事による名誉棄損等の配信サイト運営者に対する責任については、第二審判決が提供した枠組みの中で議論されることが想定されます。インターネット上のニュース配信サイトの隆盛に伴い、本分野の事例は今後蓄積されていくものと思われますので、引き続き注視していく必要があります。
(荘司 晴彦)
Ⅲ. Column
“文化芸術の中にある法を訪ねて(13)” 下関と「ふく」
下関は、かつて長門の国、長州と呼ばれていた本州の最西端の、そのまた最も西側に位置する海峡の街です。本州と九州とを隔てる関門海峡に面した山口県内最大の都市で、日本海と瀬戸内海とを結ぶ海路、本州と九州とを結ぶ陸路の十字路という地政学上の要衝にあり、古来から幾度となく歴史の大舞台に登場し、まさに歴史の宝庫となっています。源平最後の合戦となった壇ノ浦の戦いは、下関の沖合に浮かぶ満珠島、干珠島付近の海域が激戦の舞台となりました。開戦当初は日本海から瀬戸内海に向かって東に流れ込む急流に乗った平家の船団が戦いを優位に展開していましたが、潮目の急変により戦況が一変し、最後は源氏の大勝利に終わりました。平家物語には「波の下にも都は候ぞ」との女官の言葉に促されて幼い安徳天皇が入水するという涙を誘う場面が語られており、その慰霊を弔うべく竜宮城を模したという赤い楼門で有名な赤間神宮が海峡の古戦場に向かって建立されています。また、江戸時代初期の宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘で有名な巌流島(船島)も関門海峡に浮かぶ小島です。武蔵は下関側から小舟で対決の場に乗り付けたと伝えられていますが、現在はその同じルートを渡船が運航しています。さらに時代を下ると、幕末にも幾多の事件の舞台となりました。長州藩と英仏蘭米4か国の連合艦隊とのいわゆる馬関戦争の戦場となりましたし、市内の城下町長府にある曹洞宗の古刹功山寺は、高杉晋作が奇兵隊を率いて挙兵し、長州藩の守旧派を放逐して、明治維新の幕開けとなった場所として有名です。司馬遼太郎の『竜馬がゆく』や『花神』など明治維新を扱った一連の作品にはその舞台として下関がしばしば登場します。私財を投げうって尊王攘夷の志士たちを支援し続けた豪商として知られる白石正一郎の邸宅も下関にありました。赤間神宮に隣り合わせた場所には春帆楼という老舗料亭があります。ここは、1895年(明治28年)に、日清戦争終結後の講和条約(いわゆる下関条約)が締結された会場となったことで知られています。日本側の全権大使は長州出身の伊藤博文、清国の使節代表は李鴻章でしたが、併設されている日清講和記念館には条約の締結会場が再現されており、その雰囲気を感じることができます。
さて、この春帆楼は、現在ではフグ料理の専門店としても全国的に有名な料亭となっています。かつて長州藩ではフグを食することが禁じられていました。これは、文禄・慶長の役に際して東国から集結した兵士たちの死亡事故が相次ぎ、豊臣秀吉により取られた措置と言われており、江戸時代を通じてこの禁令は続けられていたようです。しかし、現在では冬の代表的な味覚の一つとなっており、「東のアンコウ、西のフグ」と並び称されるほどです。両者はいずれも見かけとは異なり、白身の上品な味で、鍋料理の具材として最高級品であることには多くの人の異論がないところと思われます。また唐揚げにした際の何とも言えぬふっくらとした食感にも共通するものがあり、食べることの幸せを十分に感じさせてくれる逸品です。このように魅力ある食材として我々を楽しませてくれる両者ですが、大きな違いもあります。その一つが肝に含まれる毒の有無です。一般にあん肝と呼ばれるアンコウの肝は珍重される絶品です。これを味噌仕立ての出汁に溶かし込んで作るどぶ汁は食通の間でも垂涎の料理です。他方、フグの肝には、テトロドトキシンという猛毒が含まれており、フグ毒についての知識が十分でなかった時代にはこれにより落命する人も少なくありませんでした。関西では、フグのことを「テッポウ」とも呼びますが、これは「当たると死ぬ」ということにかけたネーミングで、刺身を「テッサ」、鍋物を「テッチリ」と言うのも、これに由来します。
現在では、このフグ毒についての医学的な解明がかなり進み、その危険性は一般にも広く認識されるところとなっていますが、それでも未だにその解毒方法は発見されていません。ただ、フグ毒が人の神経を麻痺させ、呼吸器系の障害により致命傷を与えるとの中毒の機序については既に明らかにされており、中毒症状が生じたときは、まず気管切開や人工呼吸などの処置により呼吸を確保する救命措置を講じて、体内からの毒の排出を待つというのが基本的な対処方法とされています。かつてフグ毒に関する一般的な知見が必ずしも確立していなかった時代には、「フグ一尾に水一石と言われるほどの大量の水で洗い流せば毒は抜ける」とか、「症状が出たときには、水分を大量に摂取させて、毒の排出を速めるのが良い」などという科学的な裏付けのない俗説や素人療法もかなり広く信仰されていたようですが、考えてみると大変恐ろしい話です。
決して多くはありませんが、フグによる中毒を巡る裁判がいくつか見られます。フグを販売した者や調理人、料理店の経営者などが刑事事件として業務上過失致死傷罪に問われた事案があり、さらには、これらに加えて救急搬送された病院や治療に当たった医師に対して損害賠償を請求するという民事訴訟も提起されています。責任を肯定した裁判例がある一方で、昭和40年代に至っても、保健所でさえ調理方法と分量を規制する程度で、肝を提供すること自体は容認していたなどの理由を挙げて予見可能性を否定し、料理を提供した調理人の責任を否定した大阪高裁の判決(昭和45年6月16日)もあり、裁判所の判断は事案により分かれているというのが実情でした。その後、フグ毒についての医学的な解明が進むにつれて、フグを提供した者の責任を肯定するのが一般的な流れとなりましたが、このような中毒の危険性について多くの人たちが知るようになってからも、食通と言われる人たちの間では依然としてフグの肝を珍重する傾向が見られ、微量の肝を溶かし込んだタレに浸してフグを食し、中毒症状によりピリピリとする舌先のしびれ感、刺激を楽しむという人もいたようです。
このフグ中毒を巡る著名な裁判として、歌舞伎界の重鎮であり、人間国宝であった八代目坂東三津五郎の中毒死事件があります。被害者は、美食家としても名を知られた存在でしたが、数名のひいき客とともに京都市内の料理店でトラフグの刺身や肝臓を食べたところ、被害者だけに中毒の症状が出て、呼吸麻痺に陥り死去するという事件が発生し、料理店の調理師が業務上過失致死などの罪で起訴されました。訴訟ではフグ毒による死亡の予見可能性の有無が主たる争点となって最高裁まで争われましたが、被害者が著名人であったことも相まって、この裁判は大きな社会的注目を集めることになりました。そして、1審の京都地裁(昭和53年5月26日判決)、控訴審の大阪高裁(昭和54年3月23日判決)とも有罪の判断をしていたのですが、最高裁も「調理師は、テトロドトキシンの危険性や解毒法がないことを認識しており、フグ中毒が発生することも認識していた」、「死亡の結果が生じることまでの認識がなくても、中毒症状を起こすことを認識していれば過失致死の罪は成立する」として、業務上過失致死罪の成立を認めました。他方、「被害者のような食通とされる人たちは肝料理を提供しないと納得しない傾向が見られること」、「フグ中毒の個人的・身体的事情」を考慮して、執行猶予付きの禁固刑とした控訴審の判断を正当として支持しています(最高裁昭和55年4月18日判決)。また、この事件に関連して、遺族からは料理店の経営者と調理師を被告とする損害賠償を求める民事訴訟も提起されましたが、京都地裁は、被告らの責任を肯定する一方で、フグの肝に毒が含有されていることを被害者は承知して食しており、その量も同席した相客より多量であったことを考慮して、損害の3割について過失相殺をした上で、賠償請求を認容しました(昭和53年12月19日判決)。
フグのシーズンは「彼岸から彼岸まで」と言われ、秋分から春分までの間が旬とされています。フグの水揚げ量日本一を誇る下関市の南風泊(はえどまり)港では、袋競り(ふくろぜり)と呼ばれる独特の方法で入札が行われます。毎年、秋分の時期の初競りはニュースなどでも取り上げられ、下関の秋の風物詩の一つとなっていますので、ご存じの方も多いのではないかと思います。袋競りとは、値段の駆け引きが周囲の人に分からないように、売り手と買い手とが黒い筒状の布袋の中で指を握り合って値決めをする独特の入札方法を言います。これまで述べてきましたとおり、フグは我々の食文化に彩りを添えて、豊かにするという大きな貢献をしてきた一方で、油断すると大きな禍をもたらすという存在でもありました。「禍福はあざなえる縄のごとし」という言葉もあるとおり、幸福と禍とは直ぐ隣り合わせの関係にあります。地元下関では、縁起を担いで「福」に繋がるようにという強い願いを込めて、「フグ」と濁らずに「ふく」と呼び、2月9日を「ふくの日」としています。愛嬌のある表情で人気の「ふく提灯」は、禍福とは上手に付き合うことの大切さを教えてくれているのかも知れません。なお、実はあまり知られていませんが、アンコウも下関が水揚げ量日本一とされており、「東のアンコウ、西のフグ」の水揚げがともに日本一というのは下関市民の隠れた自慢の種となっています。
(奥田 隆文)
【編集後記】
✧ 令和も7年目を迎え、その間、様々な法規制や判例法理が積み上げられてきておりますが、社会が高度化・複雑化し続けていることに伴い、新たな法律問題は常に存在しています。今回Lawyer’s Pickで取り上げたニュース配信サイト運営者の配信記事に係る責任をめぐる裁判もその一例です。決してゴールのない世界であるからこそ法律はやはり面白いと思う反面、時代の流れに取り残されないよう、常にキャッチアップし続けていかなければならないと身が引き締まります。 ✧ 今月13日より、いよいよ、大阪・関西万博が開幕します。1970年の大阪万博は、日本の高度経済成長と科学技術の進歩を世界に示し、歴史的なイベントとなりましたが、当時の万博は、新しい科学技術や世界各地の文化を一堂に集めて多くの人々に周知し、更なる産業文化の発展を促す役割を担っていました。その後、万博の主眼は、単なる科学技術や文化の紹介にとどまらず、地球温暖化をはじめとするグローバルな社会課題にどう対応するかといったテーマに移ってきています。大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」であり、「いのち」をキーワードとして、環境問題や、多様な人々が共生できる社会、そしてそうした未来社会を実現するための様々な技術を紹介し、考えるきっかけを与えることが目的とされています。様々な議論を呼んできた万博ですが、万博をきっかけに人々が未来社会の共創に意識を向けられるような、意義ある成功を収めることに期待したいところです。 ✧ 森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業 文化芸術プラクティスグループでは、皆さまのご意見等をお待ちしております。Culture & Arts Newsletter / Mori Hamada Culture & Arts Journalへの掲載内容へのご質問のほか、誌面への感想、取り上げてもらいたいテーマ等のご要望も大歓迎です。 |
- 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
- (令和7年1月29日)映画・アニメ分野の制作に携わるクリエイターと制作会社との取引等に関する情報提供フォームの設置について | 公正取引委員会
- 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
- 裁判例結果詳細 | 知的財産高等裁判所 - Intellectual Property High Courts
- 令和6年度における日本遺産の点数評価プロセスの結果を公表します | 文化庁
- 裁判例結果詳細 | 知的財産高等裁判所 - Intellectual Property High Courts
- (令和7年3月5日)株式会社アトレに対する警告について | 公正取引委員会
- 「音楽教育を守る会」は、音楽教育事業を営む7つの企業・団体(一般財団法人ヤマハ音楽振興会、株式会社河合楽器製作所など)が発起人となり、JASRACによる音楽教室における著作権料徴収の動きに対応するために、2017年2月に結成された団体です。
- 音楽教室規定に関する音楽教育を守る会とJASRAC の合意について
- 「使用料規程」とは、利用区分(著作物等の種類及び利用方法)ごとに利用者から徴収する使用料の額等を定めたものです(著作権等管理事業法13条1項)。
- 使用料規程の一部変更に関するお知らせ
- 「演奏」の使用料については、規程上、生演奏のみならず録音物の再生も徴収の対象とされています。
- 同法は、2024年5月に公布された改正法案により、2025年4月1日から法律の題名が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(通称「情報流通プラットフォーム対処法」)へ変更されています。なお、本ニュースレターで引用する同法の規定については、当該改正の影響はないものと解されています。
- その他、「発信者」に該当しないとしても、同項本文及び各号に定められている責任限定の要件に該当するか否かについても争点とされています。